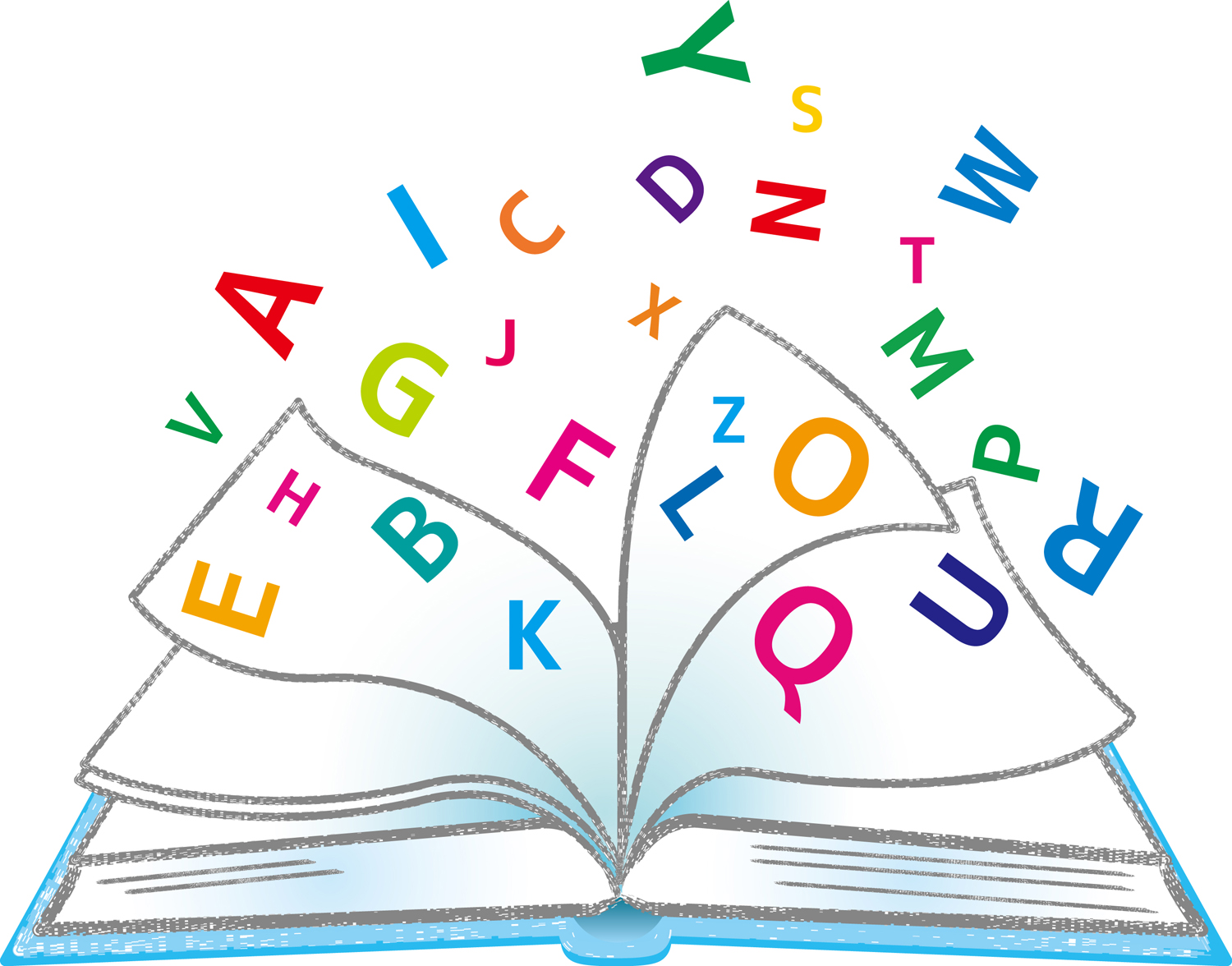2025年4月17日
【現役プロ講師が解説】英語長文の受験対策!出題傾向・読み方・おすすめ教材まとめ
目次
はじめに
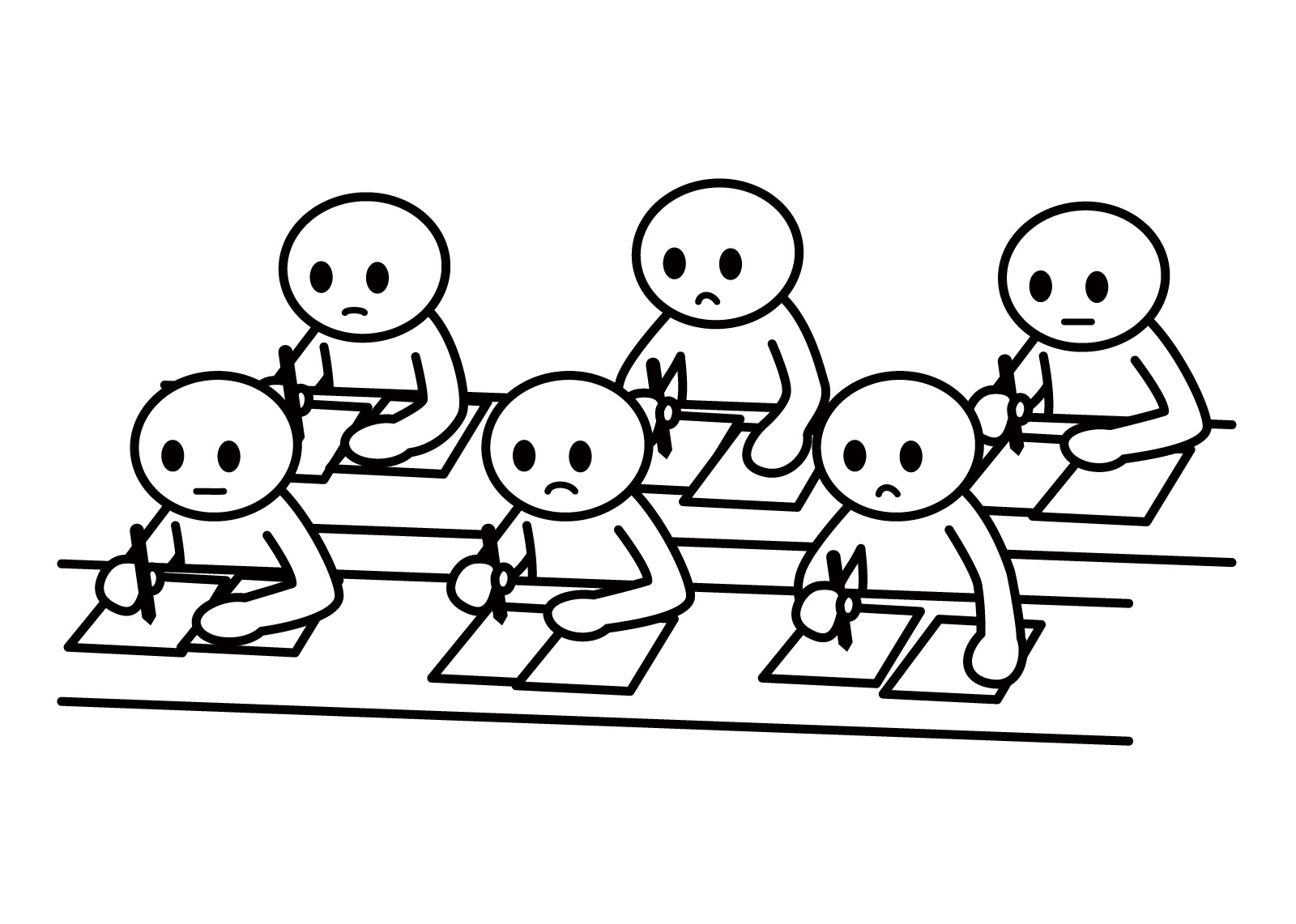
受験英語において英語長文読解は、合否を大きく左右する重要な分野です。特に大学受験・高校受験ともに、出題の大半は英語長文が占めるケースが増えており、しかもその割合は年々高まっています。
しかし、多くの受験生にとって「英語長文」は非常に高いハードルに感じられるものです。「単語がわからない」「読むのに時間がかかる」「内容が頭に入らない」などの悩みを抱える受験生は後を絶ちません。一方で、英語長文を攻略できた生徒は、試験全体の得点力が大きく向上し、安定した成績を出せるようになることが数多くあります。
現代の入試では、文法や単語の単発知識ではなく、複数の情報を統合しながら読み取る「読解力」が強く求められています。まさに、英語長文対策は英語学習の総合力を養う最高のトレーニングとも言えるのです。
本記事では、現役プロ講師の視点から英語長文の出題傾向、苦手克服のための勉強法、そして厳選された教材を網羅的に解説していきます。今の時点で「読めない」「苦手」と感じている方も、正しい方法と積み重ねで必ず克服できますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 英語長文が得点源になる時代へ
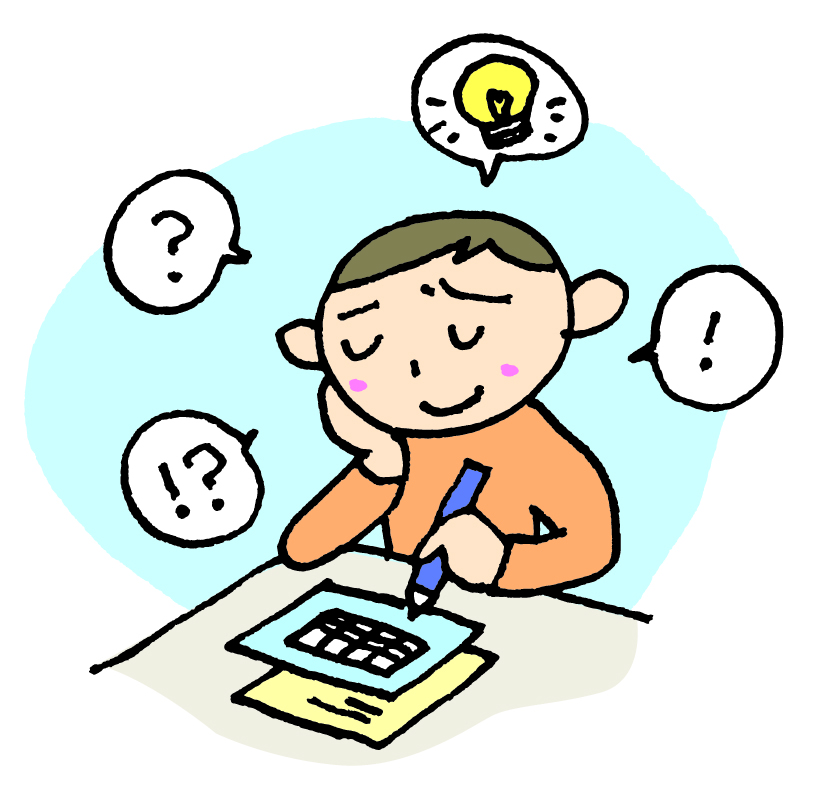
かつての受験英語では、単語の知識や文法の知識を問う問題が大半を占めていました。短文の穴埋め問題や整序英作文、文法選択問題が主流であり、文章全体を理解する力よりも「部分的な知識」が問われていた時代だったのです。しかし現在、大学入試も高校入試もその傾向は大きく変わっています。
長文読解問題が重視されるのは、英語を「実際に使う力」を測るのに最適な方法だからです。長文問題は実力の差が出やすく、入試での判断材料としても適しています。単語や文法だけでなく、文章全体の流れをつかんだり、内容を正しく理解したりする力が求められます。また、特に大学では、英語の資料や論文を読む機会が多く、読解力が必要になる場面は常日頃から多くあります。これからの時代、英語力はますます重要になるので、しっかりと読解の力を身につけておきましょう。
具体的に、各試験でどのように英語長文が出題されているのかを見てみましょう。大学入試共通テストでは、2021年以降「英文全体を読んで要点を把握する問題」や「図表や会話と組み合わせて解く問題」が増加しました。特に設問数が多く、読む英文の総語数が5000語を超える年もあり、短時間で大量の英文を読み取る力が求められています。
英語長文に対して苦手意識を持っている受験生は多いですが、それを逆手に取って「得点源」にできるようになれば、大きなアドバンテージになります。 なぜなら、文法問題や英作文は差がつきにくい一方、長文は設問数も多く、配点も高いため「得点の伸びしろ」が非常に大きいからです。
実際、偏差値60以上の難関校に合格した生徒の多くが「英語長文で点が稼げるようになった」と口をそろえます。つまり、長文読解力を武器にすることで、英語全体のスコアが底上げされ、合格ラインに近づくのです。
さらに、英語長文の力は他教科にも波及効果があります。たとえば論理構成の理解力、資料を読み取るスキル、限られた時間で要点をつかむ処理能力などは、英語長文のトレーニングを通じて磨かれていきます.
逆に言えば、「英語長文を苦手なまま放置していると、受験全体の失点要因になってしまう」のが今の入試です. そのため、できるだけ早い段階で英語長文に取り組み、得意科目に育てることが、合格への近道と言えるでしょう。
2. 英語長文が苦手な原因とその解決策
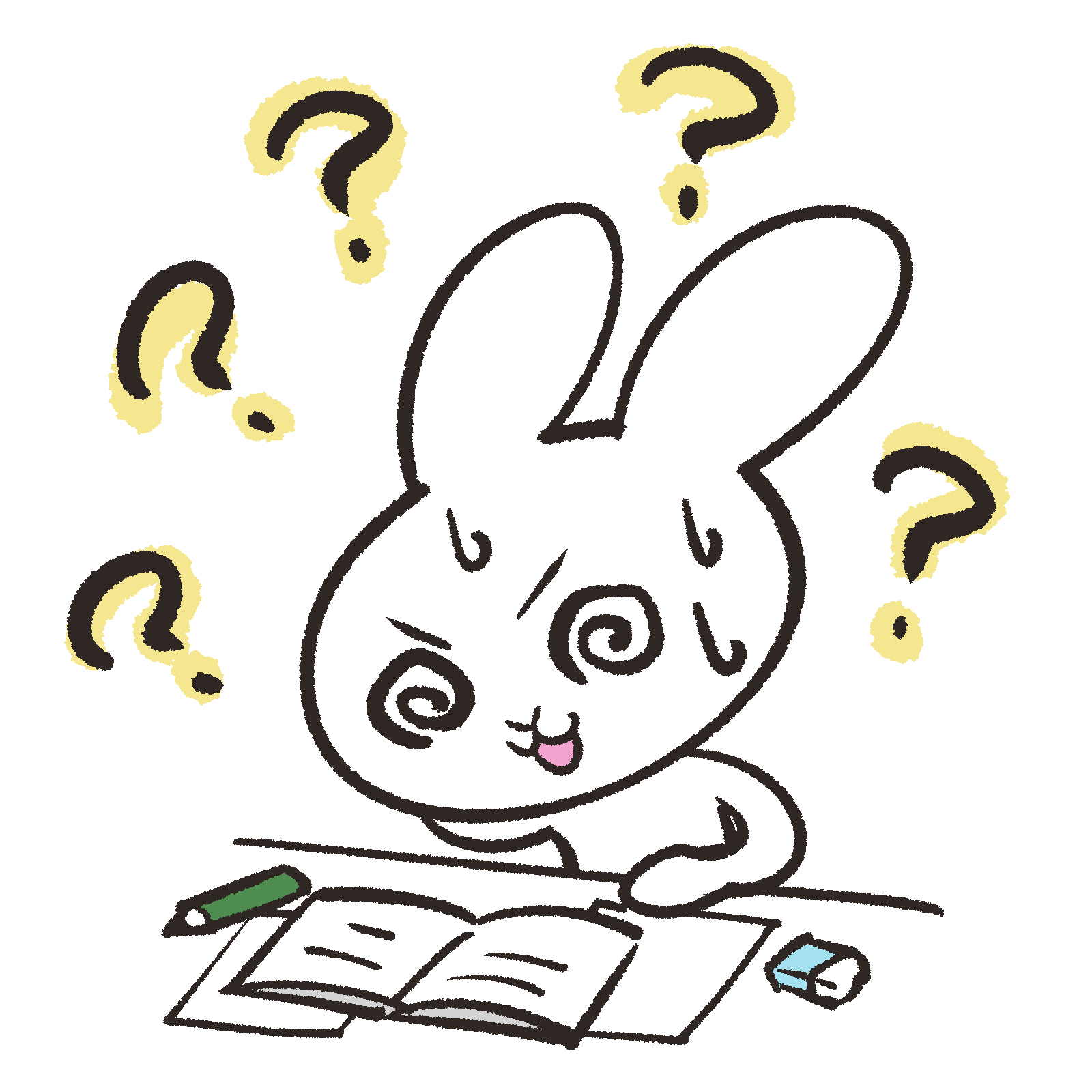
英語長文に苦手意識を持つ受験生は非常に多く、その要因は人それぞれですが、大きく分けるといくつかの共通パターンがあります。本セクションでは、特に多くの生徒がつまずく3つの原因に焦点を当て、それぞれに対する具体的な克服策を紹介していきます。
英語長文の読解において、語彙力の不足は致命的です。簡単な目安として、300語前後の長文中に出てくる単語の意味が3つ分からなければ、文全体の正確な理解は不可能になると思ってください。英文は単語が連なって意味をなしており、安易な推測は大意把握から遠のく可能性を高めます。特に入試問題では出題者の思惑通り引っ掛け問題で失点することにつながります。
「英文は読めるけど時間が足りない」という声も多く聞かれます。これは、頭の中で一語一語を訳してしまう「逐語訳読み」の習慣が影響していることが多いです。長文精読トレーニングの初期やイディオム等がまだほとんど身についていない時期では仕方ありませんが、この読み方ではスピードは出ません。
読解速度を上げるには、まず英語の語順に慣れることが重要であり、そのために有効なのが「スラッシュリーディング」と「音読」です。スラッシュリーディングとは、意味のかたまりごとにスラッシュ(/)を入れて読む方法で、視覚的にも内容が整理されやすくなります。
例:
The boy / who was wearing a red cap / ran quickly / across the field.
このように文を区切って読むことで、英文全体の構造を瞬時に把握する練習になります。
また音読は、英語の処理速度を高めるうえで非常に効果的です。目で読むだけでは気づかない「文構造の違和感」や「意味の取り違え」を、声に出すことで明確に感じることができます。加えて、音読はリズム感や語順の定着にもつながり、英語脳を鍛えるのに最適なトレーニングです。
英語長文で特に難しいのが、「文章全体の流れがつかめない」という悩みです。一文一文は理解できているのに、全体を通して何を言いたいのかが分からないという状態です。
これは「ロジカルリーディング(論理読解)」の力が不足していることが原因です。日本語は、世界の言語の中でもハイコンテクスト言語と評されます。つまり、行間や文脈で意味を補う文化が日本語にはありますが、ローコンテクスト言語の代表格である英語は非常に論理的な構造です。段落ごとに明確な主張があり、それを支える理由や具体例が論理的に配置されています.
そのため、段落ごとの主張を把握する「パラグラフリーディング」の視点を持つことが重要です。各段落の最初の1〜2文(トピックセンテンス)に注目し、「この段落では何が主張されているのか」を意識して読むだけでも、全体の論理構造がつかみやすくなります.
また、接続詞(however, therefore, in contrastなど)や指示語(this, that, suchなど)に注意することも、論理の流れをつかむ上で欠かせません。これらの語句は文と文、段落と段落をつなぐ橋渡しの役割を果たしており、筆者の意図や文章の展開を示す手がかりとなります。
さらに、読み終わった後に「この文章のテーマは何だったか?」「結論は何だったか?」を自分の言葉で要約してみる習慣を持つと、読解力は飛躍的に向上します。
3. 偏差値別・レベル別の長文読解勉強法
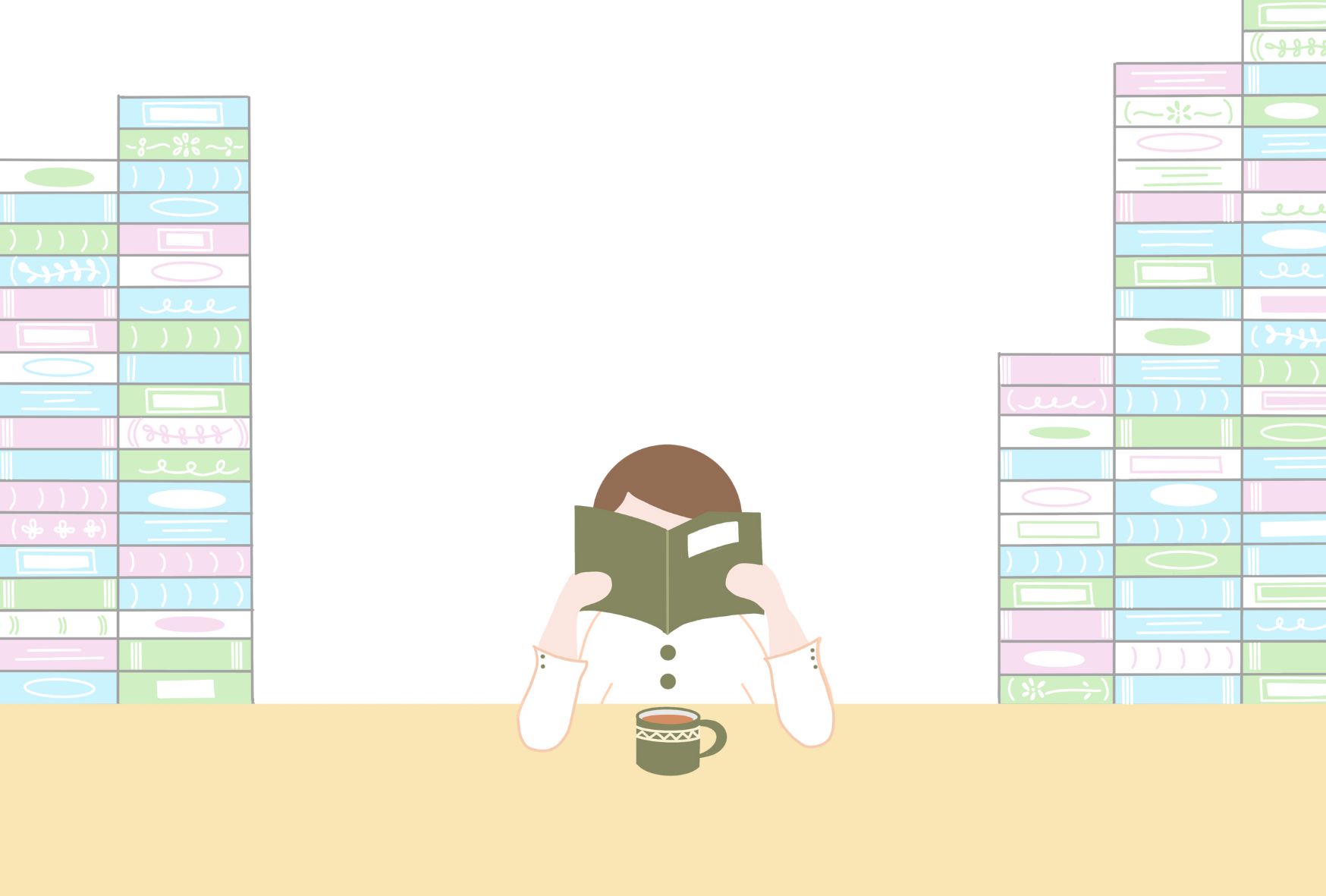
英語長文読解の勉強法は、現時点での実力によって検討すべきです。すべての受験生に同じ教材や方法を当てはめても、効果は限定的になってしまいます。このセクションでは、偏差値帯別にどのようなアプローチが有効かを詳しく解説し、各レベルの生徒にとって最適な学習法を提示していきます。
偏差値50未満の段階では、「英文が読めない」「読んでも意味が取れない」といった悩みがつきものです。この段階ではまず、「英語を学ぶのが苦痛でなくなる」ことを優先しなければなりません。
その第一歩は、語彙の習得です。注意していただきたいのは、必ず自分の実力に見合う単語帳(薄いものが望ましい)を用意することです。単語の学習は、終わりの無い茫洋とした海のようなものです。英語ができなくて苦しんでいる状況でそんな大洋に投げ出されて不安に苛まれない人はいません。だからこそ自分にもできそうなレベルで短期間で何周も回せる単語帳を使い、現実的なゴールが近くにあることを自身に認識させて安心感を担保するのです。各単語を発音し、瞬時に意味を言えたらOKです。長くても3ヶ月以内に最低6周程度のスピードでひたすら回していきます。
また、中学英文法の復習も必須です。短期間で全体を体系的に把握するためにも薄い参考書を使ってください。ここでのポイントは用法の名前ではなく、訳し方を頭にいれることを最優先することです。
例えば不定詞。名詞的用法・形容詞的用法・副詞的用法なんてことは長文が読めるようになってからでいいのです。大切なのは「こと・ために・ための」という3つの訳し方を覚えているかどうかなのです。
この段階では、長文も100〜200語程度の短いもので十分です。とにかく「最後まで読めた」という達成感を味わい、読解に対する抵抗感を減らすことが大切です。辞書や単語帳、文法書全てを駆使して全文を自力で理解しきる経験を積んでください。
座学が苦しいなら、音読だけでも効果は確実に出ます。意味がわかる短文を声に出して繰り返し読むことで、語順の感覚と英語独特のリズムが身につきます。
このレベルに入ると、英語への抵抗は減ってきていますが、「正確さとスピードの両立」に課題を抱える生徒が多くなります。また、設問を読み違える、選択肢に惑わされるといった問題も頻出します。
この段階では、300〜500語程度の中編長文を扱う教材を使い、設問付きの問題を精読することが効果的です。
また、文の構造(SVOC)や指示語・接続語を意識することは必須ですが、1つの文が数行にわたる長さの場合、"and"や"or"およびカンマを正確に対比で把握できずにいい加減な訳をする人があまりにも多いです。またSVの後に付くタイプの分詞構文を動名詞と区別をつけられず、有耶無耶にしてしまうようなことも頻繁に見受けられます。
このレベルではスラッシュリーディング、そして返り読みを絶対にせずに英語の語順で読み進める習慣を完全に身につけることが最低限の義務です。また、特に和訳書き出し問題への解答等でしっくり来ない場合は品詞分解を行ってみてください。そして、副詞(および句・節)を排除したおおもとのSVだけにして構造を把握すれば「この意味以外は有り得ない」訳読ができるはずです。
偏差値60を超えてくると、「ただ読むだけ」では通用しなくなります。ここでは「論理を読み取る力」や「要点を抽出して整理する力」が勝負の分かれ目になります。
まず扱う長文のレベルも、800語を超えるものが標準になります。アカデミックな話題(環境問題・科学・哲学など)や抽象的なテーマも頻出し、語彙だけでなく背景知識も問われるようになります。
この段階では、読解と並行して「英語で要約を書く」「段落ごとの主張を書き出す」など、アウトプット型の学習が非常に効果的です。読んだ内容を他人に説明できるレベルに落とし込むことで、読解がより深まり、記憶にも残りやすくなります。
また、「英英辞典」に挑戦するのもおすすめです。新しい単語を英語で理解する習慣は、英語的な発想を身につける助けになります。さらに、難関校特有の「推論型設問」や「言い換え問題」などに対応するため、正確な文構造の把握と論理展開の読み取り力を強化しましょう.
音読やシャドーイングも継続しつつ、週1回は時間を測って模試形式での演習を行いましょう。本番での実戦力を鍛えるには、あえて厳しい条件下でのトレーニングが不可欠です。
このレベルでは「英語を読む力」だけでなく「情報を処理し、まとめる力」も試されます。読解を通して思考力を鍛える意識を持ちましょう.
4. 読解力を伸ばす5つの学習ステップ
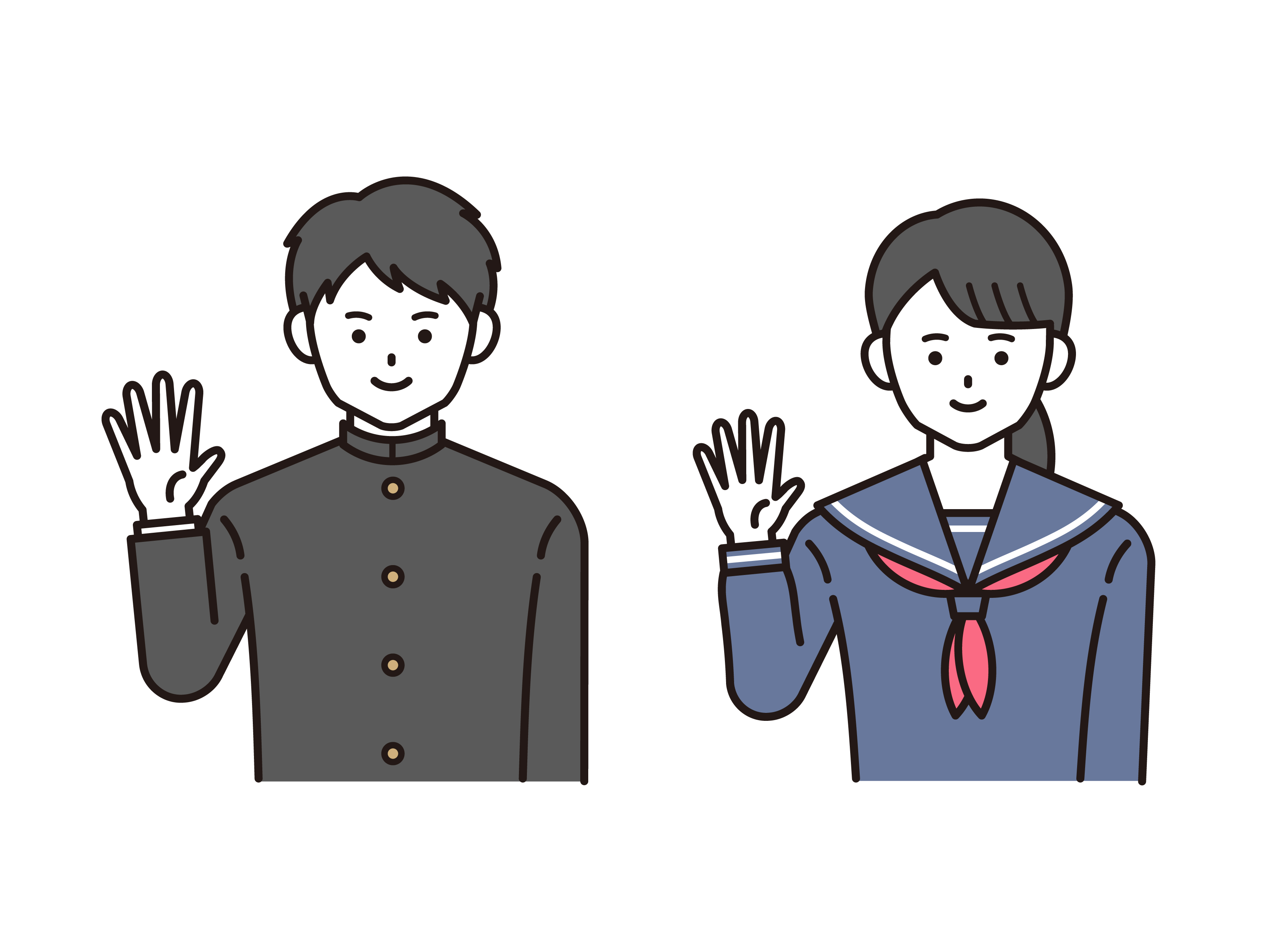
英語長文を理解するには、基礎的な語彙力と構文力が不可欠です。文章は単語と構文の組み合わせによって成り立っているため、どちらが欠けても意味の把握に支障をきたします。
語彙については、まずは日常的に使われる基本単語(2000語レベル)を中心に、繰り返し覚えることが大切です。重要なのは「意味の丸暗記」ではなく、「例文で使い方を理解する」こと。これにより、長文の中で単語の意味を文脈に合わせて柔軟に捉えられるようになります。
構文に関しては、「文型(SVO, SVCなど)」「関係詞の使い方」「分詞構文」など、長文で頻出のパターンを理解する必要があります。特に、複雑な構文が絡むと一文の意味が取りにくくなるため、文の骨格を把握する力(=構文力)を高めることで、長文全体の読解効率も格段にアップします。
日本語は後ろから修飾されることが多いのに対し、英語は基本的に前から順に意味が構成されます。そのため、英語を日本語に逐語訳するクセが残っていると、内容の理解に時間がかかるだけでなく、誤訳や文意の取り違いにもつながります。
この解決策として有効なのが「スラッシュリーディング」です。英文を意味のかたまりごとに区切り(スラッシュで区切る)、前から順に内容を理解する練習を積むことで、英語を英語の語順で処理する回路を脳内に構築することができます。
例:
The boy / who was wearing a red cap / ran quickly / across the field.
このように句や節単位で区切りながら読むことで、複雑な構文もスムーズに処理できるようになり、英文の読み進めスピードも格段にアップします。
音読は、語学学習における王道とも言えるトレーニングです。目で見た文字を声に出し、耳で聞くことで、複数の感覚を使った学習が可能になります。これにより記憶の定着が強化され、英文処理のスピードや精度も高まります。
音読は「意味がわかる文章」で行うのが原則です。意味不明なまま読むのでは効果が薄く、むしろ誤った語順やアクセントが定着するリスクがあります。まずは内容を理解してから、発音を意識しつつ、5回〜10回程度繰り返すのがおすすめです。
さらに、CDや音声教材を用いた「シャドーイング(追いかけ読み)」を取り入れることで、リスニング能力の向上にもつながります。英語を耳で処理し、即座に口に出すことで、実践的な英語力が身についていきます。
英語長文の設問には、出題者の意図やひっかけパターンが存在します。設問タイプには「内容一致」「文挿入」「語句整序」「言い換え」「要約」などがあり、それぞれに対応した読み方や解き方が求められます。
たとえば、「内容一致問題」は段落ごとの要点をきちんと整理していれば対応しやすいですし、「文挿入問題」は前後の文脈をつかむ力、「語句整序問題」は構文力と語感が必要です。
出題形式に慣れるには、過去問や市販の問題集で設問形式別に演習を積むことが有効です。間違えた問題は「なぜ間違えたか」「どの選択肢がどう違うか」を分析する習慣をつけることで、応用力も高まっていきます。
どれだけ知識や技術を蓄えても、試験本番で時間内に正確に解けなければ意味がありません。したがって、最終的には「本番形式での演習」を繰り返すことが必要不可欠です。
実戦演習では、実際の試験時間を設定し、制限時間内で解き切る練習をしましょう。共通テストなら80分、私大入試なら60分〜90分の中で複数の長文を読む訓練が求められます。初めは時間に追われてミスが増えるかもしれませんが、繰り返すことで「時間配分」や「問題処理の順序」が自分の中で確立されてきます。
さらに、演習後は「自己採点」「復習」「誤答分析」を徹底しましょう。得点を伸ばす鍵は、間違えた原因を理解し、次に同じミスを繰り返さないことです。本番に向けての総仕上げとして、実戦力と安定感を同時に養っていきましょう。
5. 受験レベル別!おすすめ英語長文参考書・問題集
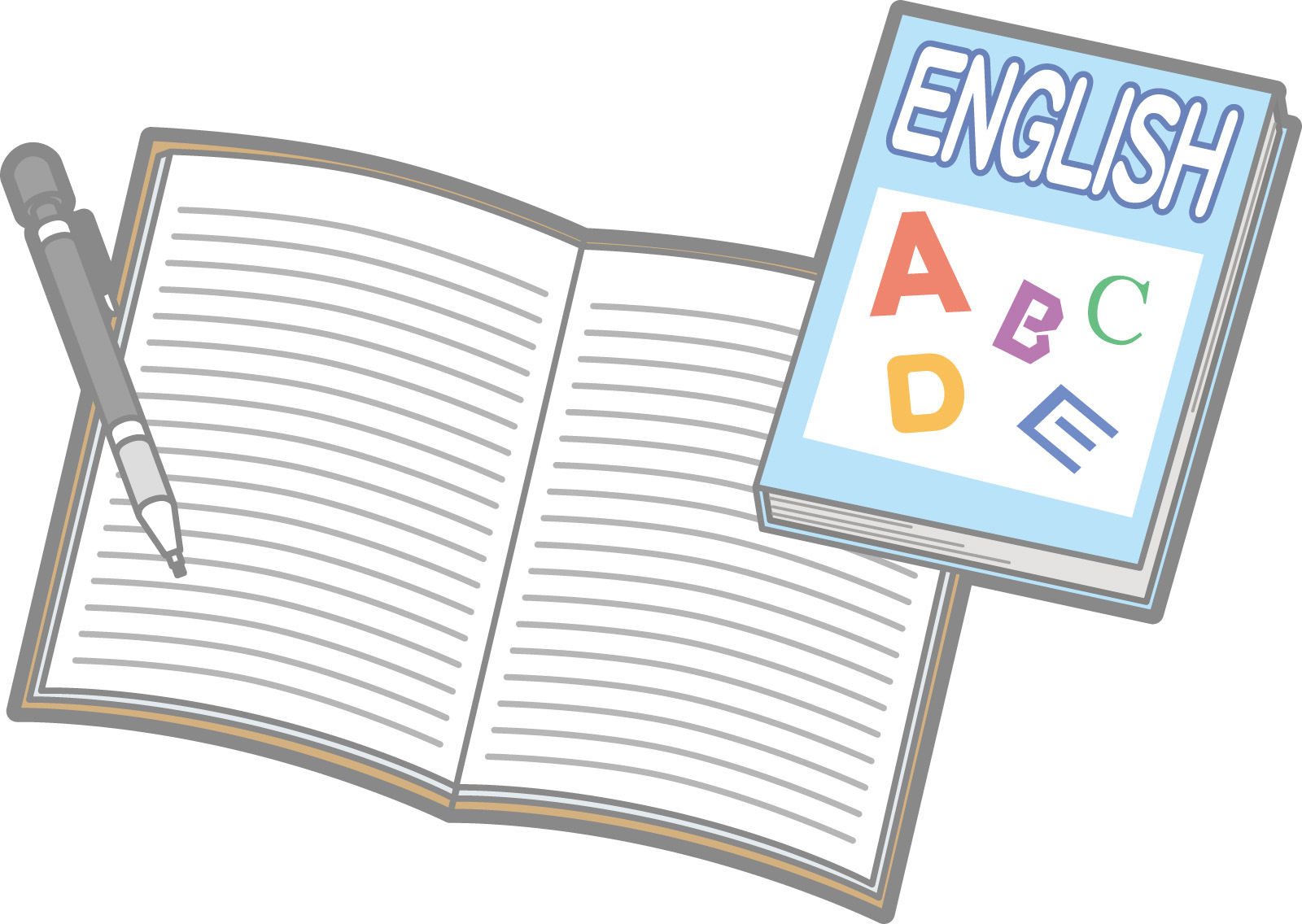
英語長文対策において、教材選びは学習成果を大きく左右します。特に長文読解では、文の構造、語彙の難易度、設問のバリエーションなど、教材によって内容が大きく異なるため、自分のレベルに合ったものを選ぶことが非常に重要です。本セクションでは、高校受験、共通テスト・中堅私大、そして難関大・医学部志望者向けの3つのカテゴリーに分けて、それぞれ最適な教材と使い方を解説します。
高校受験生にとって重要なのは、「英語長文への抵抗感をなくし、読解に必要な基礎力を固めること」です。そのためには、難解な英文よりも、身近なテーマで適度な長さの長文に触れることが大切です。
おすすめは『英語長文レベル別問題集(東進ブックス)』シリーズ。レベル1〜7まで段階的にレベル分けされており、自分の実力に合ったものを選びやすい構成になっています。文章量が少しずつ増えるので、「レベル1は読める」「レベル3で苦戦した」というように、自分の成長を実感しやすいのも大きな利点です。
『高校入試英語長文問題精講(文英堂)』もおすすめです。頻出テーマや設問パターンを網羅しており、入試に出る問題傾向への理解が深まります。特に内容一致問題や語句整序問題、空欄補充問題などの練習に適しています。
いずれの教材も、「本文を精読→設問を解く→解説で構文と語彙を確認→音読で復習」という一連のサイクルを徹底することで、知識と実践力を同時に高めることができます。
共通テストや日東駒専・産近甲龍レベルの私大を志望する受験生には、「スピード」「処理能力」「選択肢の見極め力」が問われます。したがって、問題の分量・スピード感・設問の難易度がバランス良く調整された教材を選ぶことがカギになります。
まず挙げたいのが『基礎英文解釈の技術100(桐原書店)』です。長文読解の前提として「文構造の把握」ができなければ精読はできません。本書では重要構文のパターンを100個に絞って丁寧に解説しており、長文の意味がとれない原因を根本から解消できます。
また『英語長文ハイパートレーニング(桐原書店)』シリーズは、共通テスト・中堅私大向けのベストセラー教材です。読解スピードを重視した構成で、語彙・文法・設問処理がバランスよく身につく構成になっています。特に「レベル2」「レベル3」は実戦に近い演習問題として最適です。
使い方としては、時間を計って問題に取り組み、「どこに時間がかかったか」「設問の根拠が明確だったか」を振り返ることが重要です。本文を段落ごとに区切って要点をメモする習慣をつければ、文章構造の把握力も養えます.
早慶・旧帝大・難関国公立大学や医学部レベルでは、読み手に高い「抽象的思考力」や「多義語・熟語処理力」、さらに「論理的整合性を読み取る力」が求められます。そのため、教材も難易度の高いものを選び、内容・構文ともに歯ごたえのある英文に日々触れることが不可欠です。
『ポラリス英文読解(KADOKAWA)』シリーズは、高い論理性を必要とする問題が豊富で、「内容が難しい」「設問の解き方がわからない」と感じる受験生にはとても良い訓練になります。特に医学部・旧帝大志望者はこのレベルの英文に慣れておくことが合格への鍵になります。
また『英語長文問題精講(旺文社)』は、長年多くの受験生に支持されてきた名著です。構文解析を伴う読み方を訓練するには最適で、やや古風な形式ですが、解説が非常に論理的で、読解の核を押さえる力がつきます。
難関レベルの教材では、「一文一文を精読→設問を考察→自分なりの根拠を説明する」というプロセスが重要になります。志望校の過去問も活用し、「問われ方」と「設問の正解根拠の発見」に慣れておきましょう。
教材は手段であり目的ではありません。どんな良い教材でも「読みっぱなし」「解きっぱなし」では効果は半減します。本文の再読・音読・解説確認・要約練習といった多角的な活用こそが、読解力を飛躍的に向上させる最大の武器になるのです.
6. 現場から見えた「伸びる生徒」の特徴

英語長文の指導を長年行っていると、確実に伸びる生徒と、なかなか成績が上がらない生徒の間には明確な差があることがわかってきます。生徒のタイプや性格はさまざまですが、「伸びる生徒」に共通して見られる習慣や姿勢は一定しています。ここでは、成績が飛躍的に伸びていった生徒たちの行動パターンを3つ紹介し、それぞれの具体的な実践方法もお伝えします。
英語長文読解力は、一朝一夕で身につくものではありません。日々の積み重ねこそが何より大切です。伸びる生徒の多くは、たとえ10〜15分でも「英語に触れる時間」を毎日確保しています。
その方法は様々です。具体的には、朝の通学前に1本の長文を音読したり、夜の勉強時間の最初にスラッシュリーディングを取り入れたりと、ルーティンの中に無理なく英語を組み込んでいます。短時間でも継続することで、読解スピードや語順感覚が自然と身につき、結果的に大きな伸びにつながっていきます。
英語を「勉強対象」ではなく「毎日の習慣」として捉える意識転換ができるかどうかが、最初の分岐点になります。
英単語の勉強といえば、意味の暗記が中心だと考える人も多いですが、伸びる生徒はその先を見据えています。彼らは単語を例文で覚え、文脈の中でどう使われているかまで理解しています。
模試や問題集で間違えた問題を、そのままにしていないか。ここに成績の伸びしろが表れます。伸びる生徒は、間違えた問題を「宝の山」と捉え、原因分析と復習に時間を惜しみません。
たとえば「なぜこの選択肢を選んだのか?」「本文のどの部分を読み違えたのか?」「設問の意図を正しく読み取れていたか?」といった視点で、自分の思考プロセスを振り返っています。また、正答と自分の選んだ選択肢の違いを見比べ、どの論点でミスをしたのかを明確に記録していきます。
このように「ただ答え合わせをして終わり」ではなく、「解き直し」「復習ノートの作成」「別日での再演習」まで含めて学習サイクルに組み込むことが、成績向上への最短ルートです。
7. よくある質問(Q&A)

はい。英語長文の読解力を高めるには、「量よりも頻度」が重要です。長文は、ただ1回に多く読むよりも、短い時間でも「毎日触れる」ことが脳内回路の定着につながります。たとえば、1日15分でも構いません。新聞記事の英文版、アプリの短文コンテンツ、過去問の長文などを使って、継続的に英語を読む習慣をつけましょう。
また、時間がない日でも、スラッシュを入れながら音読するだけでも十分な学習になります。読んだ後には「要点を一言でまとめる」習慣をつけることで、論理構成を掴む力も育ちます。
基本的には「並行学習」がおすすめですが、語彙力が極端に不足している段階では、まず単語帳で基礎語彙を固めることが先決です。理由はシンプルで、知らない単語が長文に多すぎると、そもそも意味が取れず、挫折につながるからです。
読解時間が足りない原因には、「処理スピードが遅い」「内容把握に時間がかかる」「設問への根拠探しに時間がかかる」など、複数の要素があります。これらの改善には、段階的な対策が必要です。
まずは音読とスラッシュリーディングで、英語の語順に慣れ、処理スピードを向上させましょう。次に、問題を解く際に「設問を先読みして、読むべき情報を意識する」トレーニングも有効です。また、制限時間を設けて長文に取り組み、「段落ごとに読む時間を調整する」意識も養ってください。
演習後には、「どの段落で時間がかかったか」「設問処理で迷った箇所はどこか」をメモし、時間配分の調整に役立てましょう。
音読は英語力向上に非常に効果的ですが、「声に出すことが恥ずかしい」と感じる方も少なくありません。その場合は、家族がいない時間帯に行う、録音して自分だけで確認する、口パクで黙読音読を行うなど、やりやすい方法から始めましょう。
音読の効果は、「発音矯正」や「スピーキングの練習」だけにとどまりません。文の構造や意味の流れを体感的に理解する力、リズムや語順の自然な感覚を育てることができる点が、最も大きな利点です。
また、英文を読む際に「詰まる箇所」が可視化されるため、苦手構文の発見や改善にもつながります。1日5分からでも構わないので、音読を習慣化できれば、英語長文に対する苦手意識がぐっと軽減されるはずです。
8. おわりに

英語長文は「才能」ではなく「技術」で伸ばすことができます。
必要なのは、正しい努力と継続する力です。本記事が、英語長文に悩むすべての受験生にとって、突破口となるきっかけになれば幸いです。
赤羽で学習塾をお探しなら
- 会社名
- 進塾
- 住所
- 〒115-0055 東京都北区赤羽西1‐39‐1伊藤ビル3階
- 電話番号
- 03-5924-7747